洪水・浸水など水害時の消毒方法
濡れた家をそのまま放っておくと、あとからカビや悪臭が発生し、生活に支障が出る場合があります。まずは床下の状態を確認してください。
床下に水・泥が入り込んでいるか確認する。
畳の場合
畳の下の床板をバールなどで1枚はがす。確認した後は、元に戻すことができる。
フローリングやじゅうたんの場合
床下収納や通風口の間口から確認する。
点検口がなければ穴をあけることも必要。できれば対角線上に2つ穴が開けられると乾燥は早い。
泥の除去と床下の清掃をする。
床下の泥をかき出して洗い、消毒する。
消毒剤は、注意書きをよく読んで使う。
よく使われる消毒剤
消石灰(しょうせっかい)
湿った床下の土にまく。素手で触らない。
逆性せっけん(ベンザルコニウム塩化物)
水で薄めて家財や床材、手指の消毒に使う。原液を素手で触らない。
カビを防ぎ、とにかく乾燥を
- 床、壁、天井などに消毒用エタノール(80%溶液)をスプレーし、雑巾でふき取る。
- 家具などに使う際には、色落ちしないか目立たないところで確認する。
- 換気をよくし、火気を使わない。
- 壁も水を吸っているので中を確認する。(断熱材は一度水を含むと抜けにくい。)
- しっかり乾燥させるには最低1か月ほどかかる。(扇風機等を利用しひたすら風を送って乾かす。)

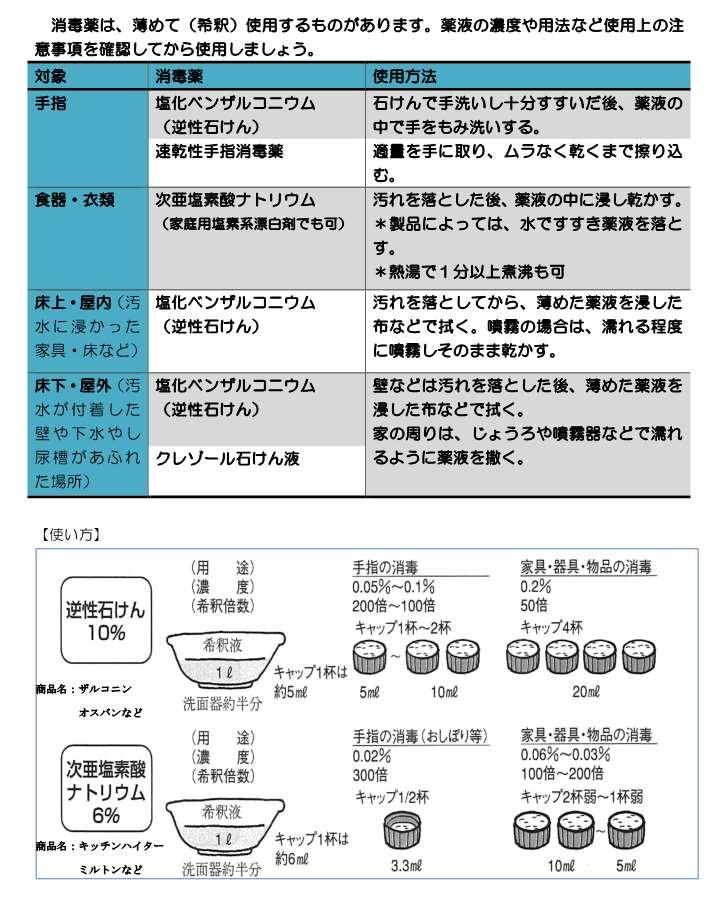
掃除をするときの服装
- 基本、肌の露出は避ける。
- 頭部:ヘルメット、防止、タオルをする。
- 目:ゴーグルをつける。特に薬品を使うとき。
- 手:ゴム手袋(中に軍手をつけると蒸れにくい。)
- 足:長靴(クギなどの踏み抜き防止インソールがあると安心)
- ヘッドライトがあると床下では便利。
- 細かい掃除には、「歯ブラシ」が便利。
- 水分補給をしっかりとる。(うがい、手洗いはこまめに)
その他参考
- 被害の様子がわかる写真を撮る。
- 家の外をなるべく4方向から、浸水した深さがわかるように撮る。
- 室内の被害状況もわかるように撮る。
- 作業の後には手指を消毒する。
- 畳、じゅうたん、布団は、水を吸うと使えない。
- 木製の棚(合板)は、乾いたように見えても、後からカビが生える。
- 水没した自動車は、絶対にエンジンをかけない。「無料で処分する」という業者に注意する。
- アルバム・写真は、しっかり洗浄、乾燥すれば復元できる場合がある。
- スマホ携帯電話は、電源を入れずに電池・カードを外し保管する。乾燥させてから携帯ショップに相談する。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 環境衛生課
電話番号:0879-26-1226
ファックス:0879-26-1336
お問い合わせはこちら




更新日:2022年04月27日